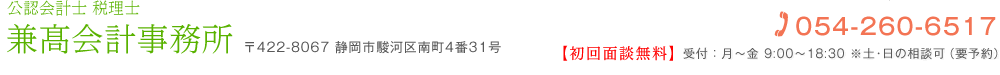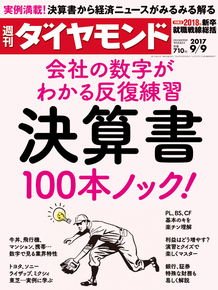【ASBJ】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表
企業会計基準委員会から、
「企業会計基準第29号『収益認識に関する会計基準』等」が公表されました。
昨年7月に公開草案が公表され、意見募集の結果を受けて、今回公表されました。
収益認識、つまり売上の計上基準に関しては、
従来は、企業会計原則に、
「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」
と規定されているのみでした。
業界ごとの慣行によっている部分もありました。
今回、会計基準を定め、こういった条件であれば売上を計上できる、ということを明確にしています。
業界・会社によっては、今後売上の計上金額が変わるかもしれません。
適用は、2021年(平成33年)4月1日以後開始する事業年度の期首からとなります。
適用まで約3年ありますので、準備を進めましょう。